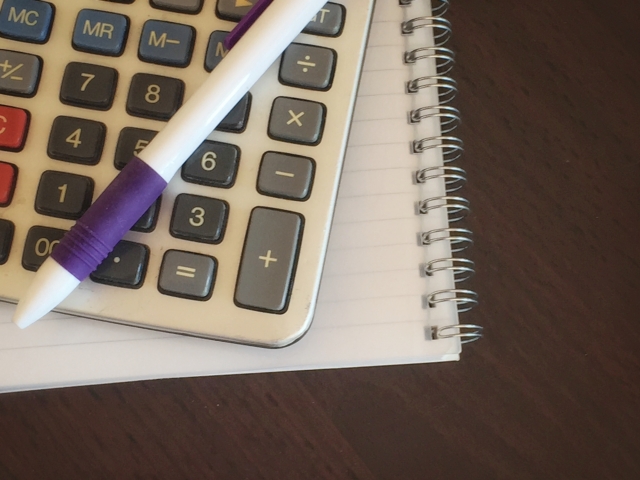【家族だからこそ】在宅介護で大変なことランキング|負担の軽減方法も解説

在宅介護とは施設に入所せず、ご家族が自宅で介護をすることです。
なお、弊社が主に提供している「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」も、入居される方は賃貸住宅を借りて在宅介護サービスを受ける形となっています。
いわば、「施設のようなサービスを受けられる在宅介護」です。
在宅介護は住み慣れた自宅や地域で生活を続けられる一方で、介護者にとって負担が大きいことも多く存在します。
この記事では、在宅介護で大変なことをランキング形式で紹介します。
負担を軽減する3つの方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
在宅介護で大変なことランキング!ワースト10を発表

在宅介護で大変なことは、ご本人の要介護度によって異なります。
要介護度とは、どの程度の介護をご本人が必要とするのかを表した指標のことです。
ここでは、要介護3(※)以上のご本人の介護者が、不安を感じる介護の項目と回答の割合について、ランキング形式で紹介します。
※排泄や入浴、着脱などの日常生活全般に困難さがあり、基本的に24時間介護が必要な状態
| 在宅介護で不安を感じること | 割合(%) | |
| 1位 | 認知症状への対応 | 35.4 |
| 2位 | 排泄介助 | 33.1 |
| 3位 | 入浴介助 | 20.5 |
| 4位 | 移動介助 | 18.0 |
| 5位 | 食事介助 | 10.9 |
| 6位 | 生活に必要な各種管理 | 7.9 |
| 7位 | 衣服の着脱介助 | 7.0 |
| 8位 | 医療的ケア | 7.0 |
| 9位 | 服薬介助 | 6.4 |
| 10位 | 身だしなみのケア | 3.8 |
なお、弊社ゴールドエイジではサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)や有料老人ホームを運営しております。
在宅介護が大変で入所先を探したいという方は、施設一覧ページをぜひご覧ください。
引用元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング|2023年 全国の在宅介護実態調査データの集計・分析結果[概要版」
1位:認知症状への対応(35.4%)
認知症の代表的な症状は、物ごとを覚えておくことが困難になる「記憶障害」と、日付や曜日などがわからなくなる「見当識障害」です。
記憶障害や見当識障害がある方は、食事をしたことを忘れたり現在の場所がわからなくなったりして、ご家族に同じ質問を繰り返します。
また、認知症状が進行すると「失禁が増える」「外出先から1人で帰れなくなる」といった行動も少なくありません。
実際、弊社運営のサ高住でも認知症の認定を受けている方はおよそ10〜25%(※)であり、適宜介護を要します。
※サービスタイプによって異なる
このように目を離せない行動が増えるため、在宅介護では認知症状への対応がもっとも大変に感じる方が多くなっているといえるでしょう。
2位:排泄介助(33.1%)
排泄介助は下表のように、日中・夜間ともに介護の大変さを感じる結果となっています。
| 介護者が不安に感じる介護 | 回答割合(%) |
| 日中の排泄介助 | 30.5 |
| 夜間の排泄介助 | 35.6 |
とくに要介護3以上の場合は下記の介助も必要であり、介護者の負担が大きくなりがちです。
- 尿意や便意の確認
- トイレまでの誘導
- 排泄後の清拭
夜間帯の排泄介助が増えると、介護者は十分な睡眠をとれないため「大変だ」と感じる場面がより一層増えるでしょう。
なお、弊社のサ高住では、夜勤者が夜間に3回部屋を訪問し、排泄介助にも対応しております。
3位:入浴介助(20.5%)
入浴介助は、身体的な負担が大きい介護の1つです。
洗身・洗髪を行う際は、介護者が中腰になったり腕を伸ばしたりして身体に負担のかかる姿勢をとります。
温かい浴室内での作業は脱水を招くおそれがあるため、ご自身の体調管理も重要です。
さらに介護者は滑る床に注意しながら、互いに転倒や転落がないよう注意する必要もあります。
不安感が高い動作だけあって、大変さを感じやすいといえるでしょう。
4位:移動介助(18.0%)
移動介助は下表のように、屋内外ともに介護の大変さを感じる結果となっています。
| 介護者が不安に感じる介護 | 回答割合(%) |
| 外出の付き添い、送迎など | 18.0 |
| 屋内の移乗・移動 | 17.8 |
移動介助には、歩行介助と車いす介助の2種類があります。
歩行介助ではご本人のバランスを崩さないよう、体を支える筋力や体力のほか、周囲環境に危険はないか注意を払うことも必要です。
一方、車いす介助は歩行介助に比べると介助者のペースで行えるものの、人が乗った車いすを押すための筋力が必要です。
また、段差や狭いスペースでは車いすを上手に操作する必要もあるため、移動介助に大変さを感じる介護者も多いでしょう。
5位:食事介助(10.9%)
食事介助については、実際の介助よりも準備に不安に感じる介護者が多い結果となっています。
| 介護者が不安に感じる介護 | 回答割合(%) |
| 食事の介助 | 30.5 |
| 食事の準備 | 35.6 |
在宅介護の場合、ご本人の好みや飲み込みの状態に合わせた、メニューの考案・調理が必要です。
施設であれば栄養士や調理師が対応するところを、在宅介護では介護者自身が自ら行う分、大変さを感じやすくなります。
また、食事を食べてもらう場面では、ご本人がムセないように、飲み込んだのを確認してから次の一口を提供することが大切です。
ご本人の状態によっては「なかなか食べてもらえない」「飲み込みに時間がかかる」などもあり、精神的疲労を感じる方も多いでしょう。
6位:生活に必要な各種管理(7.9%)
生活に必要な各種管理とは、福祉サービスに関する手続きや金銭管理などを指します。
在宅介護では、このような手続きを介護者がご本人の代理として行うケースが少なくありません。
たとえば、デイサービスなどの介護施設を利用する場合は、重要事項の説明を受ける、契約を結ぶといった行為を代行します。
実際の介護で忙しいなか、手続きに必要な時間を捻出することは介護者にとって負担が大きいものです。
7位:衣服の着脱介助(7.0%)
衣服の着脱は1日のうちに複数回行うため、介護者にとって大変さを感じやすい介護の1つです。
高齢者の場合は、老化や疾病により関節の可動域が狭くなっている場合があります。
とくに自力で動けない方の着脱介助では、ご本人が苦痛を感じないよう細心の注意を払うことが必要です。
衣類のすそを下げるため、左右順番に体を横向きにするといった、力の必要な介助が多くなる分、介護者自身の身体にも大きな負担がかかるでしょう。
7位:医療的ケア(7.0%)
在宅介護では、介護者が医療的ケアを行うケースもあります。
たとえば、ストーマ(人工肛門・人口膀胱)を造設している方の場合、介護者がパウチ内(※)の排せつ物をトイレに流したり、パウチ内を定期的に確認したりすることが必要です。
※排せつ物を受ける袋であり、ストーマ袋とも呼ばれる
医療的ケアに慣れていない場合、介護者は精神的な負担を感じるでしょう。
ただし、ご家族がすべての医療的ケアを担当するわけではありません。
訪問看護やデイサービスなどの外部サービスに医療的ケアを任せながら、在宅介護を継続することは十分に可能です。
9位:服薬介助(6.4%)
服薬介助では、薬の管理や飲み込みの確認を介護者が行います。
処方された薬の種類や服用のタイミングを事前に確認しておき、飲み忘れや飲み間違いを防止します。
疾患によっては薬の種類や数が多くなるうえ、体調に直結しやすいものもあるため、服薬介助は注意力と集中力が必須です。
その分、精神面の疲労が蓄積し、大変さを感じる要因の1つとなるでしょう。
10位:身だしなみのケア(3.8%)
歯磨きや洗顔といった身だしなみのケアは、排泄介助や服薬介助に比べると優先順位が低くなりがちなケアです。
しかし、いずれのケアも健康で自分らしい生活を送るうえで必要なことです。
たとえば、歯磨きを怠ると歯周病や虫歯の発生で健康な歯が失われ、食事の摂取が難しくなります。
すると、体力や認知能力の低下を引き起こし、ますます介護負担が大きくなるケースも少なくありません。
ご本人の精神状態によってはケアの拒否が多く、「しなきゃいけない」と「できない」の間に挟まれ、大変さを感じる介護者も多いでしょう。
在宅介護の大変さを軽減する3つの方法

在宅介護の大変さを軽減する方法は、以下の3つです。
- 信頼できる人へ相談する
- 自身の介護スキルを高める
- 入所施設の利用を検討する
それぞれ具体的な内容を見ていきましょう。
方法①:信頼できる人へ相談する
在宅介護の大変さを軽減するためには、まず信頼できる人を見つけて相談の機会を持ちましょう。
在宅介護の大変さを介護者1人で抱え込んでしまうと、心身に大きな負担がかかります。
最悪の場合、ご本人と共倒れしてしまう可能性も少なくありません。
介護者自身の生活を守るためにも、必要に応じて以下のような相談先に悩みを話してみましょう。
- かかりつけ医
- ケアマネージャー
- 親しいご家族や友人・知人
かかりつけ医には、医療ケアに関する具体的な相談ができます。
ケアマネジャーには、介護保険制度や介護サービスの相談が可能です。
親しいご家族や友人・知人には、人に伝えにくい本音を聞いてもらってもよいでしょう。
在宅介護を続けたい場合は、信頼できる人に相談してストレスを適宜発散することが大切です。
方法②:自身の介護スキルを高める
ご自身の介護スキルを高めることも、介護負担の軽減につながります。
介護スキルを高めるメリットは、以下の3つです。
- 安楽に介助できる
- 以前より早く介助できる
- 腰や肩を痛めにくくなる
また、ご本人とのコミュニケーションのやり方や心理的距離の作り方を学ぶのもよいでしょう。
親を介護する場合、介護者は過去の姿と現在の姿を比較して過度に期待したのち、できないと大きな失望に変わり、精神的な負担を感じやすいためです。
ご家族との関わり方も介護スキルの1つと捉えて、適切な接し方を身に付けましょう。
方法③:入所施設の利用を検討する
在宅介護に負担を感じたら、施設入所も選択肢の1つです。
施設入所によって適度な距離を保つことで、在宅介護よりも穏やかな気持ちで触れ合えるようになります。
なお、入所施設には、特別養護老人ホームや有料老人ホームといった複数の施設形態があります。
弊社ゴールドエイジで提供するサ高住のように、介護サービスを受けられつつ、在宅にいるような自由な生活が送れる施設もあるため、ご本人やご家族の希望に沿った施設選びが重要です。
具体的な探し方は、以下のとおりです。
- 担当のケアマネージャーに、評判のよい施設がないか質問する
- 家族や親戚におすすめの施設がないか質問する
- インターネットを使って入所施設を探す
- 新聞の折り込みチラシを参考にする
入念に情報収集し、ご本人に合いそうな施設が見つかった際は見学や体験利用を申し込んでみましょう。
入所までの流れや拒否があった場合の対応について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】親を施設に入れるタイミングや費用相場を解説!手順や拒否時の説得方法も
まとめ:在宅介護は大変なことがたくさん

在宅介護には、大変なことがたくさんあります。
ご本人とご家族の双方が無理をすることなく、家族の絆を深めていくためには、お互いの状況に合わせた生活を選ぶことが大切です。
在宅介護の負担を感じているなら、この機会に介護施設の入居を検討してみましょう。
なお、弊社ゴールドエイジでは、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)や有料老人ホームを運営しております。
介護施設を探している方は、施設一覧ページをぜひご覧ください。
この記事の監修

間井 さゆり
| 役職 | 内部監査室長 |
| 保有資格 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
2006年入社 ゴールドエイジの創業当初から介護事業運営に幅広く携わり、介護支援専門員、館長、内部監査員などを歴任し発展を支えてきた。
現在は内部監査室長としてゴールドエイジの介護事業運営の適正化、効率化を支えている。